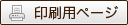最終更新日:2012年6月1日
高額療養費
高額療養費とは、後期高齢者医療制度の被保険者が、月の初日から末日までに支払った医療費の自己負担額について、以下の表1の限度額を超えたときに、超えた分が申請によりあとから支給される制度です。
保険適用分の一部負担金であれば、病院・診療所・歯科等の区別なく、少額の自己負担額でも合算されます。また、院外処方せんによる調剤の自己負担額も含めます。
ただし、入院時の食事代、おむつ代、保険のきかない差額ベッド料金、入院にかかる雑費などは合算されませんので、医療機関からの請求額合計と高額療養費の対象となる額が一致するとは限りません。
表1 窓口での負担割合と自己負担限度額(月額)
| 所得区分 | 外来 (個人ごと) |
外来+入院 (世帯ごと) |
| 現役並み所得III (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (過去1年間で4回目以降 140,100円) |
|
| 現役並み所得II (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (過去1年間で4回目以降 93,000円) |
|
| 現役並み所得I (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (過去1年間で4回目以降 44,400円) |
|
| 一般 | 18,000円 (年間上限額 144,000円) |
57,600円 (過去1年間で4回目以降 44,400円) |
| 低所得II | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得I | 15,000円 | |
※ 低所得 I とは・・・下記イもしくはロに該当する人
イ) 同一世帯の世帯員全員が住民税非課税で、世帯員の各所得が必要経費・控除を差し引くと0円になる人(年金の所得は控除額を80万円として計算)
ロ) 同一世帯の世帯員全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人
◎支給手続き
- 同封の申請書
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 通帳(口座情報の記載のあるもの)
また、一度申請すると、以後の申請は不要となり、2回目以降は支給決定通知でお知らせし、ご指定の振込先に自動的に振込みします。
入院時の窓口負担の軽減(限度額適用・標準負担額減額認定証)
村民税課税世帯の人は保険証を病院に提示するだけで、限度額が適用されますので手続き不要です。
村民税非課税世帯の人が限度額適用を受ける場合には、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、保険証とともに医療機関の窓口に提示する必要がありますので、下記により手続きしてください。
◎「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請手続き
- 保険証
- 本人の認め印
〈 申請場所 〉
- 税務住民課 後期高齢者医療係
入院時の食事代等
また、療養病床に入院する人は、表3のとおり食費と居住費を負担することになりますが、この認定証を提示すると所得区分に応じた減額がうけられます。ただし、入院医療の必要性の高い状態が継続する人等は、表4が適用されます。
| 所得区分 | 1食あたりの食事代 | |
| 現役並みIII | 460円 | |
| 現役並みII | 460円 | |
| 現役並みI | 460円 | |
| 一般 | 460円 | |
| 低所得II | 申請日より過去12ヶ月の入院日数が90日以内 | 210円 |
| 申請日より過去12ヶ月の入院日数が90日以上 | 160円 | |
| 低所得I | 100円 | |
【※】長期入院に該当するのは、過去12ヶ月以内に91日以上の入院があった場合です。(ただし、低所得 IIの区分の後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証を受けていた期間のみを数えます。)
この適用をうけるためには、上記認定証の再申請が必要となりますので、下記のものをお持ちになり、村 税務住民課 後期高齢者医療係までお越しください。(代理可)
- 保険証
- 本人の認め印
- 以前に交付された限度額適用・標準負担額減額認定証
- 入院日数を証明するもの(入院費の領収書や入院期間の証明書など)
| 所得区分 | 1食あたりの食事代 | 1日あたりの居住費 | |
| 現役並みIII | 460円(※1) | 370円 | |
| 現役並みII | 460円(※1) | 370円 | |
| 現役並みI | 460円(※1) | 370円 | |
| 一般 | 460円(※1) | 370円 | |
| 低所得II | 申請日より過去12ヶ月の入院日数が90日以内 | 210円 | 370円 |
| 低所得I | 老齢福祉年金受給者以外の方 | 130円 | 370円 |
| 老齢福祉年金受給者 境界層該当者 |
100円 | 0円 | |
| 所得区分 | 1食あたりの食事代 | 1日あたりの居住費 | |
| 現役並みIII | 460円(※1) | 370円 | |
| 現役並みII | 460円(※1) | 370円 | |
| 現役並みI | 460円(※1) | 370円 | |
| 一般 | 460円(※1) | 370円 | |
| 低所得2 | 申請日より過去12ヶ月の入院日数が90日以内 | 210円(※2) | 370円 |
| 低所得I | 老齢福祉年金受給者以外の方 | 100円 | 370円 |
| 老齢福祉年金受給者 境界層該当者 |
100円 | 0円 | |
(※1 厚生労働大臣の定める施設基準等により、420円の場合もあります。)
(※2 申請日より過去12ヶ月の入院日数が91日以上の場合は160円となります。)
(※3 指定難病の方は0円のまま据え置かれます。)
高額医療・高額介護合算制度
制度概要
しかし、その支給を受けても医療費・介護保険サービス費の両方の負担が、長期間にわたって重複している場合の世帯の重負担を軽減するため、平成20年4月から「高額医療・高額介護合算制度」が創設されました。
この制度は、1年を単位として計算期間(8月~翌年7月)の末日を基準日とし、基準日に同じ医療保険上の世帯【※1】に属している人の、医療保険・介護保険の自己負担額の年間合計から所得区分に応じた基準額を差引いた後の額を申請により支給する制度です。(ただし、総支給額が500円を超える場合に限ります。)
【※1】後期高齢者医療における医療保険上の世帯の範囲は、同じ世帯の後期高齢者医療制度に加入している人のことをいいます。
対象となる人
(1) 基準日世帯被保険者のいずれかに医療保険の自己負担額があること
(2) 基準日世帯被保険者のいずれかに介護保険の自己負担額があること
(3) 計算期間内に負担した(1)、(2)の年間合計額から所得区分に応じた基準額を差引いた後の額が、500円を超えること
また、自己負担額として算定対象となる費用額は、以下を除いた額となります。
- 医療保険の高額療養費、介護保険の高額介護(予防)サービス費の算定対象とならない費用の額(保険給付の対象とならない費用や食事代など)
- 医療保険の高額療養費、介護保険の高額介護(予防)サービス費の支給を受けることができる額や公費負担がうけられる額
手続きについて
〈 申請に必要なもの 〉
合算対象者全員の
- 認め印
- 後期高齢者医療保険証
- 介護保険証(介護認定を受けている方の分)
- 金融機関の通帳など振込先のわかるもの(被保険者本人名義のもの)
また、計算期間内において後期高齢者医療以外の保険加入期間がある場合や、転入した場合は、他の医療保険者もしくは介護保険者から申請により交付される「自己負担額証明書」の添付が必要な場合がありますので、税務住民課まで事前にお問い合わせください。
〈 申請場所 〉
- 税務住民課 後期高齢者医療係
手続きは計算期間終了後の8月から受け付けていますが、支給については事務処理の都合上、何ヶ月かお時間をいただいております。
- この支給申請には、医療費や介護保険サービス費の領収証の添付は必要ありません。
- 計算期間内に後期高齢者医療に加入歴があり、基準日現在他の医療保険にご加入の場合は、窓口に自己負担額証明書交付申請をし、基準日現在の医療保険者に提出しなければならない場合がありますので、詳しくは税務住民課 後期高齢者医療係までお問い合わせください。
療養費の支給
1. 補装具を購入した場合
支給の対象となるのは、患部の安定・固定・矯正など治療を行う上で必要な範囲のものに限られ、日常生活的なもの、職業上必要なもの、美容目的のものなどは対象となりません。
〈 支給額 〉
- 補装具の代金として支払った額の9割(現役並み所得者世帯の人は7割)
〈 申請に必要なもの 〉
- 補装具を必要とする理由を記した医師の診断書等
- 補装具購入時の領収書(上記の診断日以降に発行されたもの)
- 本人の認め印
- 金融機関の通帳など振込先がわかるもの
〈 申請場所 〉
- 税務住民課 後期高齢者医療係
2. 1. 以外の場合
- やむを得ない理由により、保険証の自己負担割合で治療を受けられなかった場合
- 骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けた場合で保険証の自己負担割合で治療を受けられなかった場合
- あんま、マッサージ、はり、きゅう等の施術をうけた場合(医師の同意が必要)
- 生血の輸血をした場合
- 海外渡航中に病気やけがで治療を受けた場合
〈 支給額 〉
- 医療費として支払った額の9割(現役並み所得者世帯の人は7割)
〈 申請に必要なもの 〉
- 場合により必要なものが異なりますので、税務住民課 後期高齢者医療係までお問い合わせください。
〈 申請場所 〉
- 税務住民課 後期高齢者医療係
その他の給付
主治医の指示による訪問看護は、保険証の自己負担割合で利用することができます。
b. 保険外併用療養費
高度先進医療を受けたときなどは、一般治療と共通する部分については医療保険が適用され、保険証で治療が受けられます。保険適用外の部分の費用は全額自己負担となります。
c. 移送費
特定の医療機関でなければ受けられない治療が必要であったなど、緊急やむを得ない理由で、医師の指示による転院などの移送に費用がかかったとき、広域連合が必要と認めた場合に限り支給されます。
d. 特別療養費
被保険者が資格証明書を受けている場合、医療費はいったん医療機関の窓口で全額負担することになりますが、申請により自己負担額を除く分が特別療養費として支給されます。
● お問い合わせ先 税務住民課 後期高齢者医療係 電話 0175-27-2111
葬祭費の支給(お亡くなりになったとき)
〈 支給額 〉
5万円
〈 申請に必要なもの 〉
- 申請者(喪主等)の認印
- 申請者(喪主等)の金融機関の通帳など、振込先がわかるもの
※ 申請者以外の口座に振込みしたい場合は、委任状が必要です。
※ お亡くなりになった方に対して高額療養費などの給付費が発生した場合の受取人を指定していただく「受領申立書」も、葬祭費の支給申請時に合わせて記入していただきます。
〈 申請場所 〉
税務住民課 後期高齢者医療係
関連リンク
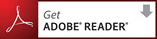
PDFのダウンロードについて
PDFファイルをご覧いただくにはAdobeReader(無償)が必要です。AdobeReaderがインストールされていない場合は、左のアイコンをクリックして、ダウンロードした後インストールしてください。
AdobeReaderダウンロードページ
本ページに関するお問い合わせ先
税務住民課国民健康保険グループ
所在地:〒039-4292 青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内5番地34 [アクセス]
電話番号:0175-27-2111
Fax番号:0175-27-2299
メールアドレス:zeimu-kokuho@vill.higashidoori.lg.jp