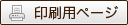最終更新日:2012年4月1日
この制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。
児童扶養手当を受けることができる人
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達した後最後の3月31日まで)を監護している父又は母若しくは父母に代わって児童を養育している人が、児童扶養手当を受けることができます。
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父又は母が死亡した児童
(3)父又は母が重度の障害にある児童
(4)父又は母の生死が明らかでない児童
(5)父又は母から1年以上遺棄されている児童
(6)父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童 【※平成24年8月から】
(7)父又は母が1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらないで懐胎した児童
(9)母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童(孤児等)
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父又は母が死亡した児童
(3)父又は母が重度の障害にある児童
(4)父又は母の生死が明らかでない児童
(5)父又は母から1年以上遺棄されている児童
(6)父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童 【※平成24年8月から】
(7)父又は母が1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらないで懐胎した児童
(9)母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童(孤児等)
次のような場合は手当を受けることができません。
児童が
◆児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき。
◆父又は母に支給される公的年金の加算の対象になっているとき。
父又は母若しくは養育者が
◆婚姻の届出はしなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき(父又は母に限る)
申請手続きに必要なもの
児童扶養手当は、児童を監護している父又は母若しくは養育者が役場を通じ申請し、知事の認定を受けることによって申請した翌月から支給されます。
(1)児童扶養手当認定請求書(健康福祉課にあります)
(2)請求者と対象児童の戸籍謄本
(3)請求者と児童が含まれる世帯全員の住民票(続柄、マイナンバーの表記があるもの)
(4)印鑑及び金融機関の預金通帳(請求者本人名義のもの)
(5)所得課税証明書(1月1日以降転入された方)
(6)その他必要な書類
※ 詳しくは、健康福祉課にお問い合わせください。
(1)児童扶養手当認定請求書(健康福祉課にあります)
(2)請求者と対象児童の戸籍謄本
(3)請求者と児童が含まれる世帯全員の住民票(続柄、マイナンバーの表記があるもの)
(4)印鑑及び金融機関の預金通帳(請求者本人名義のもの)
(5)所得課税証明書(1月1日以降転入された方)
(6)その他必要な書類
※ 詳しくは、健康福祉課にお問い合わせください。
手当の額
【令和7年度4月】
【令和6年度4月】
※所得額に応じて全部支給と一部支給があります。
※児童が2人以上のときは、1人増えるごとに11,030円加算されます。
| 区分 | 児童1人 | 児童2人目以降 |
|---|---|---|
| 全部支給 | 46,690円 | 57,720円 |
| 一部支給 | 11,010円 から 46,680円 |
5,520円 から 11,020円 |
【令和6年度4月】
| 区分 | 児童1人 | 児童2人 | 児童3人 |
|---|---|---|---|
| 全部支給 | 45,500円 | 56,250円 | 62,700円 |
| 一部支給 | 10,740円 から 45,490円 |
5,380円 から 10,740円 |
3,230円 から 6,440円 |
※児童が2人以上のときは、1人増えるごとに11,030円加算されます。
所得の制限
請求者及び扶養義務者の前年(1月から6月までの請求は前々年)の所得が、下表の所得限度額を超える場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、児童扶養手当は一部又は全額が支給停止となります。
本体額:0.0256619
第2子以降加算額:0.0039568
※所得制限限度額は、下記の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて変わります。
【所得制限限度額表】※令和7年4月分以降の児童扶養手当の一部支給額を算出するための係数は、以下の通り
本体額:0.0256619
第2子以降加算額:0.0039568
※所得制限限度額は、下記の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて変わります。
| 扶養親族等の数 | 請求者本人 | 養育者 配偶者 扶養義務者 |
|
|---|---|---|---|
| 全部支給 | 一部支給 | ||
| 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
| 以降1人につき | 380,000円加算 | ||
| 加算額 | 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族 1人につき 100,000円 特定扶養親族 1人につき 150,000円 |
老人扶養親族1人につき(当該 60,000円 |
|
手当の支給時期
年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)、【11日】に指定された金融機関口座へ振り込まれます。
※11日が土日祝日の場合は直前の銀行営業日となります。
※11日が土日祝日の場合は直前の銀行営業日となります。
手当を継続して受けるために必要なこと
現況届(役場から通知が行きます)
児童扶養手当を受給又は支給停止されている方は、毎年8月に前年所得や扶養の状況などを記載した現況届を提出しなければなりません。この届は8月からの1年間、手当が支給されるかどうか審査するものです。
※この届出をしないと、手当が受給できなくなります。
※この届出をしないと、手当が受給できなくなります。
一部支給停止適用除外事由届(村から通知が行きます)
児童扶養手当を受給し始めてから5年以上が経過している方が対象で、下記に該当する場合に関係書類とともに提出が必要です。もし、提出がなかった場合は支給額が一部停止となります。
1 就業している場合
2 求職活動等の自立を図る活動をしている場合
3 身体上又は精神上の障害がある場合
4 負傷又は疾病等により就業が困難な場合
5 児童や扶養親族が障害、負傷、疾病、要介護等の状態にあり、介護を行うため就業が困難 な場合
1 就業している場合
2 求職活動等の自立を図る活動をしている場合
3 身体上又は精神上の障害がある場合
4 負傷又は疾病等により就業が困難な場合
5 児童や扶養親族が障害、負傷、疾病、要介護等の状態にあり、介護を行うため就業が困難 な場合
手当を受けることができなくなる場合
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに健康福祉課まで届出てください。
1 受給者が婚姻したとき(事実婚含む)
2 児童が児童福祉施設等に入所したとき
3 受給者及び児童が公的年金・遺族補償を受けることができるようになったとき
4 児童を監護又は養育しなくなったとき
5 受給者及び児童が死亡したとき
6 拘禁されていた父又は母が出所(仮出所を含む)したとき
7 遺棄していた父又は母が帰ってきたとき
8 その他、受給資格要件に該当しなくなったとき
1 受給者が婚姻したとき(事実婚含む)
2 児童が児童福祉施設等に入所したとき
3 受給者及び児童が公的年金・遺族補償を受けることができるようになったとき
4 児童を監護又は養育しなくなったとき
5 受給者及び児童が死亡したとき
6 拘禁されていた父又は母が出所(仮出所を含む)したとき
7 遺棄していた父又は母が帰ってきたとき
8 その他、受給資格要件に該当しなくなったとき
その他
次のような場合は、役場への届出が必要です。
1 他の市町村へ転出するとき
2 受給資格がなくなったとき
3 住所、氏名、振込先金融機関を変更したとき
4 児童扶養手当の証書をなくしたとき
5 受給者が死亡したとき
※ 以上に該当する方は、必ず健康福祉課まで届出て下さい。また、詳細については下記までご連絡ください。
1 他の市町村へ転出するとき
2 受給資格がなくなったとき
3 住所、氏名、振込先金融機関を変更したとき
4 児童扶養手当の証書をなくしたとき
5 受給者が死亡したとき
※ 以上に該当する方は、必ず健康福祉課まで届出て下さい。また、詳細については下記までご連絡ください。
本ページに関するお問い合わせ先
健康福祉課福祉グループ
所在地:〒039-4222 青森県下北郡東通村砂子又里17-2 [アクセス]
電話番号:0175-28-5800
Fax番号:0175-48-2510
メールアドレス:kenkou@vill.higashidoori.lg.jp