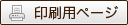最終更新日:2021年11月19日
国民健康保険(国保)とは
わたしたちは、病気やケガをしたときに安心して「公的保険」により治療が受けられるよう、かならず、いずれかの保険に加入しなければなりません。
国民健康保険は、勤務先の健康保険・共済組合等に加入している方や後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方を除いた全ての方が対象となります。
国民健康保険(国保)に加入するかた
〇パートやアルバイトなど職場の健康保険などに加入していない方
〇3カ月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の方
国民健康保険に加入する場合(加入日)
(1)他の市町村から転入(前住地で国保であった場合)・・・転入した日から
(2)職場を離職したとき・・・・・・・・・・・・・・・ 離職日の翌日から
(3)子供がうまれたとき・・・・・・・・・・・・・・・ 出生日から
(4)生活保護が廃止となった・・・・・・・・・・・・・ 生活保護廃止日から
国民健康保険を喪失する場合(喪失日)
(1)他の市町村に転出したとき・・・・・・・・・・・・・・転出した日(県内)
転出日の翌日(県外)から
(2)会社に就職し健康保険等に加入したとき・・・・・・・・加入した日の翌日から
(3)後期高齢者医療に加入したとき・・・・・・・・・・・・加入した日の翌日から
(4)死亡されたとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・死亡した日の翌日から
(5)生活保護の受給者となったとき・・・・・・・・・・・・生活保護開始日から
国民健康保険の届け出について(加入・喪失)
国民健康保険への加入、喪失の事由が発生した場合は、必ず14日以内に税務住民課・国民健康保険の窓口に届け出して下さい。この届け出を怠った場合、二重に保険料を収めることになったり、遡って国民健康保険税を納めることになる場合があります。また、資格喪失後に国民健康保険証で医療機関を受診した場合、後日、医療費を返還していただく場合がありますので、会社に勤めるなどして新しい医療保険に加入した際は、速やかに国民健康保険の資格喪失の手続きをしてください。
※職場の健康保険に加入した場合は国民健康保険への届け出が必要です!!
国民健康保険では自動的に資格喪失にはなりませんので、必ず届け出をお願いします
届出に必要なもの
| 事由 | 届出に必要なもの | ||||||
| 国民健康保険に加入する場合 | ・村外から転入したとき | ・旧住所地の転出証明書 | |||||
| ・職場を離職したとき | ・職場の健康保険等を喪失した証明書 (職場で発行します) |
||||||
| ・子供が生まれたとき | ・国民健康保険被保険者証 | ||||||
| ・生活保護を受けなくなったとき | ・生活保護廃止決定通知書 | ||||||
| 国民健康保険を喪失する場合 | ・村外へ転出するとき | ・国民健康保険被保険者証 (必ず返却してください) |
|||||
| ・職場の健康保険等に加入したとき | ・国民健康保険被保険者証(返却) ・職場の健康保険等に加入した証明書 (職場で発行します) ・職場の健康保険証(証明書が無い場合) |
||||||
| ・死亡したとき | ・国民健康保険被保険者証 | ||||||
| ・生活保護を受けたとき | ・生活保護開始決定通知書 | ||||||
国民健康保険被保険者証について
国民健康保険に加入された方には『青森県国民健康保険被保険者証』を交付します。(70~74歳の方には『青森県国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証』を交付します。)被保険者証は国民健康保険に加入している証明であり、1人に1枚の個人カードです。紛失したり破れたりしないよう大切に取り扱ってください。また医療機関で受診する際は忘れずに持参してください。
保険証の再交付手続きについて
国民健康保険被保険者証を紛失したり、盗難にあった場合、破損あるいは印字が読みにくくなったときは、申請により窓口で再交付を受けることができます。
◎手続きに必要なもの
- 本人の身分確認ができるもの(運転免許証またはマイナンバーカードなど)
- 汚れたり破損した保険証(保険証が残っている場合)
国民健康保険被保険者証の一斉更新について
国民健康保険被保険者証の有効期限は毎年7月31日までとなっており、1年間で更新となります。
令和3年8月1日から新しい保険証となり、これまでの薄橙色(うすだいだいいろ)から『水色』のものとなります。
新しい保険証は令和3年7月下旬に発送する予定となっています。
国民健康保険で受けられる給付
| 70歳~74歳までの人 | 2割~3割 |
| 義務教育就学後~69歳までの人 | 3割 |
| 義務教育就学前まで | 2割 |
療養費
・やむを得ない事情により、保険証の自己負担割合で治療をうけられなかった場合
・骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けた場合
・医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代
・あんま、マッサージ、はり、きゅう等の施術をうけたとき
(医師の同意が必要)
・生血の輸血をした時の費用
・海外渡航中に病気やけがで治療を受けたとき
申請に必要なもの
・国民健康保険被保険者証・領収書
・世帯主の預金通帳
・世帯主および受診者のマイナンバーカードまたは通知カード
高額療養費
70歳未満の方の自己負担限度額
| 所得要件 | 区分 | 自己負担限度額 | ※多数該当 |
| (国保加入者の基礎控除後の | |||
| 総所得金額等を合計した額) | |||
| 901万円を超える | ア | 252,600+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
| 600万円超~901万円以下 | イ | 167,400+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
| 210万円超~600万円以下 | ウ | 80,100+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
| 210万円以下 | エ | 57,600円 | 44,400円 |
| 住民税非課税 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
※多数該当・・・診療月から過去12カ月以内に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合 。
70歳以上75歳未満の自己負担限度額
| 区分 | 個人単位 | 世帯単位 |
| (外来のみ) | (入院含む) | |
| 現役並み所得者III | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | |
| ※多数該当の場合140,100円 | ||
| 現役並み所得者II | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | |
| ※多数該当の場合93,000円 | ||
| 現役並み所得者I | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | |
| ※多数該当の場合44,400円 | ||
| 一般 | 18,000円 | 57,600円 |
| (年間144,000円上限) | ※多数該当の場合44,400円 | |
| 低所得者II | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者I | 8,000円 | 15,000円 |
※多数該当・・・診療月から過去12カ月以内に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合
・現役並み所得者III・・・・・住民税の課税所得が690万円以上の方
・現役並み所得者II・・・・・住民税の課税所得が390万円以上の方
・現役並み所得者I・・・・・住民税の課税所得が145万円以上の方
・一般・ ・・・・・・・・・住民税の課税所得が145万円未満の方
・低所所得者II・・・・・・・住民税非課税世帯で、低所得者I未満の方
・低所所得者I・・・・・・・住民税非課税世帯で、世帯主及び国民健康保険加入者全員の所得が0の方(公的年金の場合は80万円以下)
高額療養費の算定方法
以下の(1)~(3)の順で算定された金額の合計が支給されます。(1)70歳以上の被保険者の外来の自己負担額を個人で合算し、個人単位で自己負担限度額を超えた額
(2)70歳以上の被保険者の自己負担額を世帯で合算し、世帯単位で自己負担限度額を超えた額
(3)70歳未満の被保険者の自己負担額と70歳以上の被保険者の自己負担額(世帯単位の自己負担限度額までの額)を世帯で合算し、70歳未満の自己負担限度額を超えた額
※診療が月をまたいだ場合、それぞれ各月ごとの計算となります。
※70歳未満の方は、同一の医療機関(入院・外来・歯科は別々)で、同一月内の保険診療の自己負担の合計が21,000円以上となった場合に合算の対象となります。
※高額療養費の自己負担には、食事代や病衣代、室料は含みません。
高額療養費の申請に必要なもの
・国民健康保険被保険者証・世帯主名義の通帳等(振込口座情報がわかるもの)
・医療機関が発行した領収書
・世帯主および受診者のマイナンバーカードまたは通知カード
『高額療養費のお知らせ』について
高額療養費の支給対象となる方には、『高額療養費のお知らせ』を送付しています。お知らせを受け取った方は、申請に必要なものを持参のうえ、税務住民課 国民健康保険窓口で申請してください。
※『高額療養費のお知らせ』を送付するまでには、診療月から約3カ月ほど時間を要しますのでご了承ください。
入院時の食事代等
なお、すでに「標準負担額減額認定証」の交付を受けている、70歳未満で住民税非課税世帯のかた及び、70歳以上で住民税非課税世帯のうち低所得者IIの該当となるかたは、入院日数が91日以上となった時に、長期入院の認定を受ける申請をすることができます。
入院時の食事代の標準負担額
| 所得区分(※1) | 標準負担額(1食あたり) |
| ・下記以外の人 | 460円 |
| ・住民税非課税世帯(区分オ) | |
| ・低所得者II | 210円 |
| (過去12ケ月の入院日数が90日までの場合)) | |
| ・住民税非課税世帯(区分オ) | |
| ・低所得者II | 160円 |
| (過去12ケ月の入院日数が90日を超える場合(※2)) | |
| ・低所得者I | 100円 |
限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けるには、次のものをお持ちの上、国民健康保険の窓口(即日交付可)で手続きをしてください。
申請に必要なもの
・交付を希望する人の国民健康保険証
・手続きする人の本人確認書類
・世帯主及び受診者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
なお、有効期限後、引き続き「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を希望される人は、再度ご申請ください。その際、上記のものに加えてお持ちの「限度額適用・標準負担額減額認定証」をご持参ください。
※ 交付される証は、食事の標準負担額減額認定と、医療機関の窓口で支払う一部負担金が自己負担限度額までで済む限度額適用認定を兼ねています。
長期認定の申請について
長期認定の申請は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請に必要なものの他に、90日を超えた入院であることを証明するもの(医療機関で発行した領収書等)が必要となります。
出産育児一時金
被保険者が出産した場合には、子供1人につき40万4,000円が支給されます。(※流産や死産の場合でも妊娠12週以上の時は支給されます。)また、産科医療補償制度加入の医療機関等で出産(在胎週数22週以上)した場合は、1万6,000円を加算して支給されます。
・出産費用が42万円未満で収まった場合は、その差額を申請により後日支給します。
直接支払制度をご利用しない場合は、退院時に出産費用を全額お支払いしていただいたうえで、出産育児一時金を申請し、世帯主に支給となります。
•保険証
•世帯主の預金通帳
•病院の領収書
•医療機関との直接支払に関する契約文書
•死産の場合は、医師の証明書
葬祭費
申請に必用なもの
・死亡された方の国民健康保険被保険者証
・喪主名義の通帳(口座情報のわかるもの)
その他の給付
移送費
重病人を緊急に搬送するなど、やむを得ない理由で、医師の指示による転院などの移送に費用がかかったとき、保険者が必要と認めた場合に限り支給されます。
特別療養費
被保険者が資格証明書の発行を受けている場合、医療費は医療機関の窓口で全額負担することになりますが、申請により自己負担額を除く分が特別療養費として支給されます。
ジェネリック医薬品ご利用のお知らせ
ジェネリック医薬品をご存知ですか?
医療機関等で処方される薬には、「新薬(先進医薬品)」と「ジェネリック医薬品(後発医薬品)」があります。ジェネリック医薬品は、先発医薬品と同等と認められた医薬品で、新薬と同じ有効成分・効能・効果を持つ後発医薬品です。新薬の特許が切れた後に販売されるため開発費用が抑えられることから、一般的に新薬に比べ価格が安くなっています。
このため、ジェネリック医薬品を選ぶことで自己負担が減り、村の医療費を減らすことに繋がります。
ジェネリック医薬品への変更については、直接医師や薬剤師に相談してください。
『ジェネリック医薬品希望カード』について
「ジェネリック医薬品希望カード」は医療機関等の窓口で保険証または診察券と一緒に提示することで、処方される薬をジェネリック医薬品に変更することができます。
「ジェネリック医薬品希望カード」は保険証の一斉更新の際に保険証と一緒に同封している緑色のカードです。国民健康保険の窓口にも備えてありますので希望する方はお問合せください。
交通事故にあったとき(第三者行為)
しかし、この場合の治療は、本来加害者(第三者)が負担するべきものなので、治療費のうち国保の負担分は、国保が一時的に立替払いし、後日加害者に請求することになります。
そのため、交通事故で負傷されるなど、第三者行為の原因として医療機関等で国保の保険証を使って治療を受ける場合は、必ず国民健康保険の窓口へ届出をしてください。
また、やむを得ない事情で届出をする前に医療機関を受診する(した)場合は、負傷の原因が第三者の行為によるものであることを医療機関に申し出てください。
届出に必要なもの
・交通事故証明書又は交通事故証明書入手不能理由書
・第三者行為による傷病届
・事故発生状況報告書
・念書
・保険証
・印鑑
注意事項
・相手方(加害者)が不明の場合でも届け出てください。
・ご自身の過失の大小に関わらず、届け出てください。
・示談などをしようとするときは必ず、事前にご相談ください。
※以下からダウンロード可能です
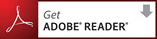
PDFのダウンロードについて
PDFファイルをご覧いただくにはAdobeReader(無償)が必要です。AdobeReaderがインストールされていない場合は、左のアイコンをクリックして、ダウンロードした後インストールしてください。
AdobeReaderダウンロードページ
本ページに関するお問い合わせ先
税務住民課国民健康保険グループ
所在地:〒039-4292 青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内5番地34 [アクセス]
電話番号:0175-27-2111
Fax番号:0175-27-2299
メールアドレス:zeimu-kokuho@vill.higashidoori.lg.jp